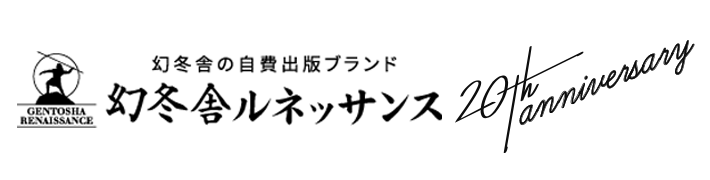本棚のある
風景
中世ヨーロッパの書籍は彼らの手から生まれた!写字生たちの姿を追う

マドリッド・ラザロ・ガルディア―ノ美術館所蔵
欧州各地に残る美しい写本の数々。
15世紀にグーテンベルクによって印刷術が世に出るまで、書籍はすべて手書きでした。
現代の私たちがこれらの写本を目にすることができるのは、1字1字を根気よく写し続けた写字生たちのおかげです。今回は、書籍の歴史を語るうえでは縁の下の力持ちともいえる、写字生たちの姿に、スポットライトを当ててみたいと思います。
ヨーロッパにおける本の変遷をざっとおさらい

フィレンツェ・ウフィッツィ美術館所蔵(筆者撮影)
まずは、ヨーロッパにおける書籍の変遷をざっと追ってみましょう。
古代における書籍は巻物が主流で、パピルスが使用されていました。塩野七生氏によれば、パピルスを切断して現代の書籍の形を考案したのはユリウス・カエサルであったそうです。しかし、「重々しい振舞」を好むローマ人たちにはこの書籍の形は定着せず、中世になって綴じの形の書籍が主流となります。
素材も、植物性のパピルスから動物の皮を原料とする羊皮紙が使用されるようになりました。中国からアラブを経由して、紙の本が普及するのは12世紀まで待たなくてはなりません。
中世の書籍が非常に高価で一部の富裕層のみが所有できる奢侈品であったのは、羊皮紙が高価であったこと、1字1字を書き写すその手間ゆえでした。
暗黒のという形容詞がつく中世は人々の識字率が低かったため、こうした写本のほとんどは読み書きができる修道院の僧たちの手によって作られていました。歴史学者のアレッサンドロ・バルベーロによれば、当時の僧たちの読書欲を満たすにはあまりに書籍の数が少なく、ゆえに彼らの記憶力は現代のわれわれの想像が及ばないほど高かったといわれています。
一介の修道僧から公爵お抱えの写字生まで

(筆者撮影)
蛮族の侵入からも書籍を守った修道院は、中世から文化の担い手であり続けました。現在も、ワインやリキュール、化粧品や食材にいたるまでメイド・イン・修道院の物産を目にすることがありますが、これは知力と人材に事欠かなかった修道院だからこそ可能であった伝統といえるでしょう。
修道院の多くには、スクリプトリウムと呼ばれた写字室が存在していました。この写字室は、修道院内でも最も窓が多く採光性の高い場所に位置していました。写字を得手とする僧たちはこの部屋にこもり、1日平均10~12ページを書き写していたそうです。もちろん、手もとが暗くなり夕暮れ後は写字の仕事はできなくなります。そのため、日中の作業が中断しないよう、写字に従事する僧たちは昼間の祈祷ミサへの参加も免除されていたほどでした。
巻物とは異なり、綴じの書籍は表と裏に文字を書くことになります。羊皮紙は動物の皮ですから、表と裏では書き心地にも相違がありました。一般的に、動物の肉に面していた方がペンの滑りがよかったと伝えられています。動物の毛が生えていた面は、ざらざらとして書きにくく、インクの色もなじみにくかったようです。
写字生を語るうえでよく例に挙げられるのが、ブルゴーニュ公フィリップ3世に仕えた文学者ジャン・ミエロです。15世紀に活躍したジャン・ミエロは、ブルゴーニュ公爵お抱えの写字生でもありました。その彼が、当時の写字室で仕事をする様子が細密画に残っています。

アルバート1世王立図書館所蔵
ジャン・ミエロが仕事をしている部屋には、まず窓ガラスが見えます。窓ガラスは古代から存在していましたが、中世になってその技術が飛躍的に向上しました。おそらく、明るい光を部屋に取り入れるだけではなく、仕事の途中でふっと目を上げれば窓の向こうに美しい自然が見えたことでしょう。
そして、部屋を暖める暖炉も見えます。意外なことですが、この暖炉は中世に生まれたものでした。公爵お抱えのエリートであるミエロは、写字室において暖炉を存分に使用できただけではなく、毛皮で裏打ちされたガウンをはおり、足元にはこれまたぜいたく品であった絨毯が敷いて仕事に没頭しています。デスクワークの敵である寒さ対策はばっちりといったところでしょうか。
筆写の仕事には不可欠なペン、まちがいを削るナイフ、文鎮となっている鉛、上部の書見台には原本が置かれ、机の周辺にも当時のエリートにふさわしく書籍があふれています。
写しまちがい発生!写字生たちの悪魔とは?

ところで、プロの写字生といえども人間、1日10ページも書き写していれば当然まちがいも発生します。修正ペンも消しゴムもなかった時代、書き間違いは写字生たちにとってそれこそ神をも呪いたくなるような事件であったにちがいありません。写しまちがいの修正は、専用のナイフで削り取るという作業も非常に煩瑣なものであったのです。
そのため、写字生たちはこのまちがいをある悪魔のせいにしていました。この悪魔、その名を「ティティヴィラス」といいます。少し愛嬌のある可愛らしい名前ですね。
このティティヴィラスの名前が最初に登場するのは1285年頃のこと。ウェールズのヨハンネスと呼ばれた神学者の著作にその姿がとどめられています。
ティティヴィラスは、毎日修道院や教会を徘徊し筆写生たちの「写しまちがい」をかき集め、背負い袋いっぱいに詰めて喜んでいたそうです。1日が終わると、ティティヴィラスはこのまちがいだらけの袋を悪魔のもとに運びます。悪魔は、写しまちがいを犯した写字生の名前を、ご丁寧にも彼のノートに記録します。そして、最後の審判が行われる日には悪魔のノートが日のもとにさらされて、写しまちがいを犯した筆写生たちの名前が声高にアナウンスされることになっていたのだそうです。
ちなみに、言葉のつづりを間違えてしまった場合には、抜けた文字を言葉の上に小さく書き込んで対応していたこともわかっています。
プロの矜持をもって仕事をしていたからこそ、写字生たちは最後の審判の日にはその裁きを受ける覚悟ができていたのかもしれません。
参照
- Medioevo dul naso Chiara Frugoni著 Laterza刊 P29-38
- Medioevo No,217 Febbraio 2015 P.86-109
- Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri Alessandro Barbero著 Laterza刊 P.3-25
このコラムの連載記事
幻冬舎ルネッサンス新社では、本を作る楽しみを自費出版という形でお手伝いしております。
原稿応募、出版の相談、お問い合わせ、資料請求まで、お気軽にご連絡ください。
-
ポイント1
お問い合わせいただきましたら、担当の編集者がご対応いたします。
-
ポイント2
原稿内容やご要望に沿ったご提案やお見積もりをご提示いたします。
-
ポイント3
幻冬舎グループ特約店(150法人3,500書店)を中心とした全国書店への流通展開を行います。