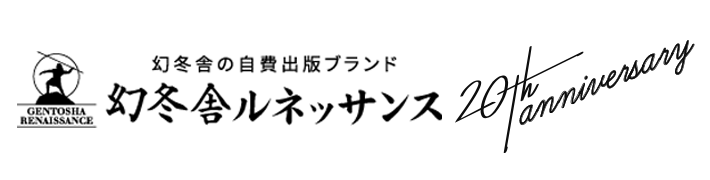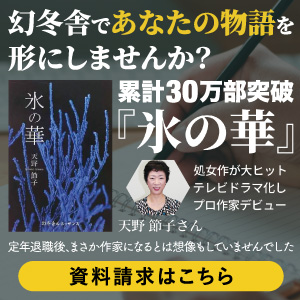コラム
僕たちだけがいない街で**
本コラムでは、幻冬舎ルネッサンス宛にご応募いただいた、読者の方からの寄稿文をお届けします。どうぞご覧ください。
気づくと、僕はこの場所にいた。この場所に至るまでの記憶がいっさい欠けている。多くの視線を感じて周囲を見回してみる。それは、様々な要素が混淆した視線ではあったが、おそらくは、突然、この場所に出現したであろう僕自身の姿を想像してみると、それらの喫驚な視線たちは、別段、奇妙ではない。むしろ、僕の方こそ驚くべきなのだ。
周囲を見渡すと同時に、街の情景を概観し、そして、僕が立っている場所の真後ろにある、解体途中の建物を見上げてみる。解体業者が瓦礫を運び出している横に、上りのエスカレーターが設けられていた。おそらくは駅であろうその入り口に書かれてある文字を読むまでもなく、僕はその場所が、僕自身の故郷であることを知る。故郷はその匂いや、風、人間に予め与えられている五感で判断できるものだ。しかし、誰かに呼ばれるように、僕が突然その姿を現した故郷の街は、僕が知っている街ではなかった。僕の記憶にある故郷の街に比して、その街はあまりにも人が多すぎた。
その場所にいつまでも止まるわけにもいかず、僕は街を歩き始めた。どこかから常に誰かが僕を見ている。その視線は、僕の自意識を肥大化させたが、数分歩いているうちに、慣れてしまった。僕は自分自身に、透明人間になる暗示を唱えたのだ。そうすると、不思議なことに、視線の非対称性はすり替わり、対象に注ぐ視線の力学の天秤は、僕の方へ傾くようになった。いまや、彼らを見ているのは、僕の方なのだ。

馴染みのない街、それでも故郷の匂いを風が運んでくる街を、僕は練り歩いた。オシャレな服飾店や雑貨店、カフェが立ち並ぶ通りを、まるで、異邦人のように物珍しそうに眺めていく。僕は店内の客たちにしっかりと視線を注ぐ。その視線を受けて彼らもこちらを見返すが、僕は彼らの視線には映らない。そう、この街には、僕だけがいない。
あるカフェに入り、四人掛けのテーブル席にひとりで座り、カプチーノを注文した。店員の物珍しそうな目つきは、逆に、僕の視線のパワーに転換される。僕はその若く綺麗な女性店員を食い入るように見る。しかしながら、彼女は注文を受けるとさっさと去ってしまった。白で統一されているらしい店内を見渡しながら、この街に至るまでの経緯を思い出そうとしてみるが、そもそも、この街に僕が出現する以前に、自分がどこに存在していたのかすら思い出すことができない。白いテーブルの上で両掌を開いては閉じる動作を繰り返し、僕は記憶を掘り起こすことを諦める。やがて、運ばれてきたカプチーノの表面に泡で描かれているミッキーマウスの絵柄を数秒見て、それを勢いよく崩した。
以前から、ミッキーマウスに同情することは度々あった。ディズニーランド内では、いついかなる時でも、ミッキーマウスはひとつの場所にしか存在できない。二体のミッキーマウスが、同時に存在してはならないのだ。僕は女の子とディズニーランドに行く度に、そのことでミッキーマウスに同情したものだ。ディズニーキャラクターが集まって、ショーをする時間になると、さっきまで園内で飛び跳ねていたミッキーマウスは、どこかへ消えなければならない。どうにかして、そのミッキーマウスをその場所に止めてあげたかったが、それには僕は無力すぎた。いつだったか、一緒にディズニーランドに行った遥子という女の子は、そのミッキーマウスに透明になる暗示を唱えていたものだ。今の僕には遥子の気持ちがよくわかる。
僕は白く無味乾燥としたカフェを出て、再び、見知らぬ街を歩き始めた。記憶の中の故郷には、たしか、映画館があったはずだ。その場所が今ではビジネスホテルに変わっている。あるひと夏に、「ミッション・インポッシブル」を三度観た映画館だった。その記憶が喚起されると、無性に映画が観たくなり、僕は見知らぬ街で映画館を探しまわった。嘗て、映画館があった場所をすべて辿ったが、この街には映画館はどこにもなかった。トム・ハンクスとメグ・ライアンがメールを介して出会う「ユー・ガット・メール」を二度観たある夏、僕はその映画館内で、ある女の子と二人きりの貸し切り状態だった。お互いに度々視線を交感し合ったが、そこから話が発展するかといえば、そんなことは微塵もなく、僕は帰京して黎明期のインターネット、そして、Eメールに夢中になる。
初めてインターネットに接続した年、老若男女問わず、僕は手当たり次第メール交換をした。そして、アドレス帳に記録した相手の名前をすべて遥子と名付けた。受信ボックスのメールはすべからく遥子からのメールだった。まったくもって、遥子からのメールは話題に事欠くことがなかった。政治的な問題から、恋愛話、果ては、生理不順についてのメールまで、話題は多岐に及んだ。僕は律儀にもそれらのメールすべてに返信をし、その文面を書いている間、常に、あの映画館で二人きりだった女の子の顔を思い浮かべていたのだった。
今、僕はその映画館があった場所に立っている。入り口横の貼り紙を読むと、どうやらそこはライブハウスに変わってしまったようだ。西の空は既に夕暮れに移行していたが、収容人数を誇るらしいそのライブハウスの前には、人だかりはまったくなかった。そこに立ち尽くしている間、僕は雑多な視線を浴びたが、透明なミッキーマウスになった今、その視線は意味を成さない。もはや、優位に立った僕の視線は、通りを歩く見知らぬ顔をすべて追った。時々、暗示を解き、ミッキーマウスとしての僕を彼らに曝してみた。すると、彼らの顔に驚きが蘇ってくるのだった。僕は再び暗示を唱え、透明なミッキーマウスになる。しかし、その女の子は、透明なミッキーマウスにじっと視線を注ぎ続け、その場所に立ち止まった。「ユー・ガット・メール」を二人きりで観た、あの女の子だった。
問題は、その女の子の姿形があのときのままだったことだ。女の子は少しずつ僕に近づいてきて、無言のまま、僕の顔をじっと見つめていた。こちらから声をかけるべくもなく、遥子は「やっぱり、あの日のままね」と僕に話しかけてきた。
「遥子はあの日のままだけど、俺は随分と時間を経てきたよ」と僕は応え、次の瞬間、自分が透明なミッキーマウスであることに気づいた。
「よく俺が見えるね」
「転送されたことにまだ気づいてないのね」と遥子は事もなげに呟いた。
「わたしとあなたは、わたしたち二人にしか見えないホログラフィなのよ」
「転送?ホログラフィ?」
「あの頃、毎晩Eメールのやり取りしてたのを憶えてる?あなたにメールを送信してたのは全部わたし。あなたの記憶にあるディズニーランドや、あなたが経てきた時空間すべてがデータベース化されてるの」と遥子は言って、少し微笑んだ。
「つまり、あなたが一緒にいた女の子は全部わたし、遥子なの。もちろん、この映画館であなたと二人きりだったわたし」
「俺の経てきた時空間がデータベース化されてるって、いったい、どこに?」
「わたしの記憶の中に決まってるじゃない」
「そして俺をあの場所に転送したの?俺の記憶はどこから消えてる?あの場所に立つ以前のことを何も憶えていないんだ」
「それについては、悪いことしちゃったと思ってるわ。ちょっと悪戯しすぎちゃったかなって」
そう言った後で、再び微笑んだ遥子は、まるで無邪気な少女のようだと僕は思った。
「記憶が所々欠けている原因はわかった。でも、遥子の姿形があのときとまるで変わっていないのはなぜ?」そう言って、僕はもう一度、遥子の顔を訝しげに見た。
「まだわからないの?あなたの記憶にもわたしがデータベース化されて保存されているからよ」
まったく、信じられない話だった。でも、僕はもしかしてと思い、遥子にふたつの質問をしてみた。
「そう、わたしから見えるあなたはあのときのままよ。そして、あなたがわたしを呼んだの、この場所に」
「俺が遥子をこの場所に呼んだ?この見知らぬ街に?」
「あなた、『ユー・ガット・メール』の記憶を辿ってこの場所まで来たでしょ?だから、わたしはあのときのまま。わたしは、あの映画を観た後で、駅でもう一度あなたを見かけたの。だから、さっきまでその記憶を思い浮かべてて、あなたをあの場所に転送しちゃったんだ、あなた、どうするのかなと思ってさ」そう遥子は応えた後で、満面の笑みを浮かべた。
「あなた、この映画館でわたしと二人きりだったときのことちゃんと憶えてる?」
「はっきりと憶えてる。時々、目線が合ったこともね」
「じゃあ、面白いことしようよ。わたしはわたしの記憶のデータベースからあのときを取り出すから、あなたはあなたの記憶のデータベースからあのときを取り出してみて」
「取り出す?具体的にどうすればいいの?」
「思い出すだけでいいの。後は勝手に事が運ぶから」
「それは、タイムスリップするという意味かな?」
「あなた、もしかして自分が存在していると思ってるの?わたしたち、どこにも存在していないただのホログラフィなのよ」
「俺たちは存在していない?意味がわからないな。じゃあ、実際の俺たちはどこにいるんだ?」
「さあ、どっかで仕事でもしているか、遊んでるんじゃない。そんなことより、昔、わたしが送信したメールの件名に『遥子です』って初めて書いたメール憶えてる?」
「もちろん、憶えてる」
「嘘つき。あなたが受信したのは全部わたしのメールで、わたしはそんな件名書いてません」そう言った遥子は、なにか企みを含んだような顔で笑っていた。
「さてさて、じゃあ、また後で」
真っ暗な館内のスクリーンには、メグ・ライアンからメールを受信したトム・ハンクスが映っている。僕は前から三段目の中央に座っており、左端を見るとそこにはあの女の子がいた。あのときと同じだ。僕たちは視線を交感し合った。そして、僕は立ち上がり、女の子に近づいて、小さな声でこう話しかけた。
「遥子だよね?」
【終】
関連記事
幻冬舎ルネッサンス新社では、本を作る楽しみを自費出版という形でお手伝いしております。
原稿応募、出版の相談、お問い合わせ、資料請求まで、お気軽にご連絡ください。
-
ポイント1
お問い合わせいただきましたら、担当の編集者がご対応いたします。
-
ポイント2
原稿内容やご要望に沿ったご提案やお見積もりをご提示いたします。
-
ポイント3
幻冬舎グループ特約店(150法人3,500書店)を中心とした全国書店への流通展開を行います。