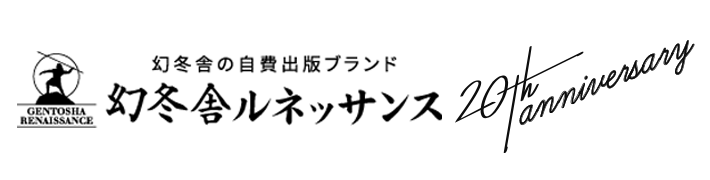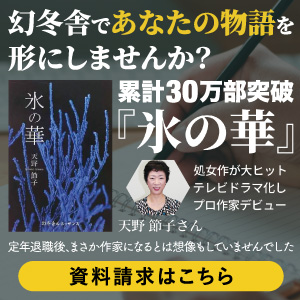コラム
3人の作家に学ぶ! プロ流ストーリーのつくり方**
「小説を書きたい」──本好きなら誰もがそう思ったことがあるのではないでしょうか。
しかし、思いつく題材はいつも何かの二番煎じ……。
そんな方も多いと思います。
今回は、一流の作家がどのようにストーリーを作っているのか分析することで、物語づくりのヒントをご紹介します。
ストーリーのつくり方① 徹底的に取材する
まずは『月と蟹』で直木賞を受賞した作家・道尾秀介氏の例を見てみましょう。
道尾氏は、ランチワゴンで生計を立てる女性を描いた作品『スタフ staph』を執筆する際に「実際に屋台村に出向き、1日3軒ほど食べ歩きながら、扇風機の回り方、電源の場所、ガスはプロパンが使われていることなど、つぶさに観察した」そうです。
(※「疾走するランチワゴンに乗って――」より)
ジャーナリストや学者も顔負けの取材力・調査力ですね。
道尾氏の魅力でもある日常への特殊な眼差しは、こうした工夫に由来しているのかもしれません。
想像だけで作品を書こうとすると、いわゆる「よくある話」になりがちです。
特に情景描写は淡泊になりがちなもの。
行ったことのない場所を作品の舞台にするなら、味気ない描写にならないよう、実際にそこを訪ねて取材してみることも、物語を深めるために重要な作業です。
ストーリーのつくり方② 自身の経験をもとにする
①とは反対に、取材はせず、自分の中にある情報から物語を組み立てる作家もいます。
『いま、会いにゆきます』がベストセラーとなった作家・市川拓司氏がその好例です。
市川氏は「黄昏の谷」(『ぼくの手はきみのために』所収)の執筆動機を尋ねられた際に「小説の舞台として自分が子どもの頃に住んでいた長屋を描きたいという理由がありました」と答えています。
(※「INTERVIEW 著者との60分」より)
市川氏はこうした方法で執筆することで、作中に登場する家族の年代記を温かみのあるものに仕上げています。
自分の記憶を掘り起こし、そこから発想を展開することで、実感のこもったストーリーを作ることができるのです。
ストーリーのつくり方③ 登場人物の視点や情報を整理する
『理由』で直木賞を受賞した作家・宮部みゆき氏は、ストーリーを語るうえで以下の点が重要であると語っています。
その事件を誰の目で体験させるか、不定的な側から見るか、面白がっている側から見るか、事件によって傷ついた側なのか、犯人なのか。あるいは世間から見るのか。もうひとつは時系列ですね、どの時点から書くか。
(『ミステリーの書き方』より)
特にミステリーのように伏線が醍醐味の作品では、「プロット」と呼ばれる物語の下書きが重要となります。
書き進めるうちに軸がぶれていかないよう、情報をはじめに確定させておくことは非常に大切です。
プロの作家でも、物語の作り方は人それぞれです。
みなさんも、ご自身に合ったストーリーの書き方を探ってみてはいかがでしょうか。
関連記事
幻冬舎ルネッサンス新社では、本を作る楽しみを自費出版という形でお手伝いしております。
原稿応募、出版の相談、お問い合わせ、資料請求まで、お気軽にご連絡ください。
-
ポイント1
お問い合わせいただきましたら、担当の編集者がご対応いたします。
-
ポイント2
原稿内容やご要望に沿ったご提案やお見積もりをご提示いたします。
-
ポイント3
幻冬舎グループ特約店(150法人3,500書店)を中心とした全国書店への流通展開を行います。