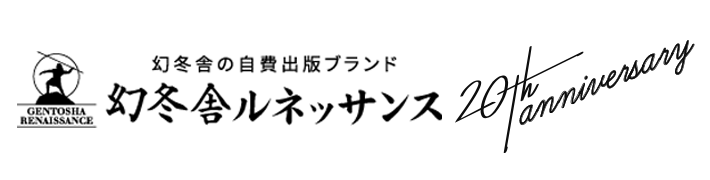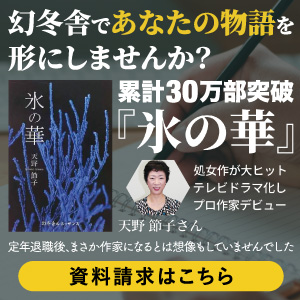漁夫
本コラムでは、幻冬舎ルネッサンス宛にご応募いただいた、読者の方からの寄稿文をお届けします。どうぞご覧ください。
もう何時間も、一人の年老いた漁師が、磯で沖をながめていた。彼は、半分朽ちて、浜に埋まったままの小舟の舳先に腰をおろし、はるかかなたに視線をおいていた。何か深い思案にふけっているようにみえた。
年老いた顔は、長い年月、海とともに生きてきた漁夫の玄太だった。はだは黒味がかった赤銅色に焼け、顔は深いしわに刻まれて、それが彼の漁師としての年輪を物語っていた。太くふしくれだったたくましい手、大きくどっしりと大地を踏みしめた足。過酷な海の仕事に耐えてきた男の風格がにじみでていた。

今日の海は、ことのほか静かであった。秋の空は抜けるように青く、遠く水平線上は空と海とが混然と一つにとけあっていた。そのあたりは、玄太が何十年もかよいつづけた海である。イワシやサンマを追い、コンブやサザエを採り、近年はめっきり少なくなったイカや寒ブリ漁に一喜一憂した海である。シケの日など彼の小舟は、木の葉のように波にほんろうされた。だから知らない人は、たいへんな危険をともなう重労働だと思うだろう。が、彼にしてみれば、漁にでているときがいちばん気持ちが充実していた。網を打ち、釣り糸をたれて海面をにらむとき、彼の頭の中に雑念など入り込む余地はなかったのである。
その海が……と、思うと
「フゥ……」
と、玄太は深いため息をついた。この海が……この海が本当になくなってしまうというのだろうか?どうしてそんなことが許されるのか?おれたちに海さがなくてやっていけるのだろうか?さっきから何度同じことを考えたことだろう。考えつかれた彼は、半分にちぎった紙巻きタバコをキセルにつめて、深々と吸い込んだ煙をはきだしながら、なんどもつぶやいていた。
「村のものたちゃあ、いったいみんな何を考えていやあがるんだ?」
彼は、昨夜のことを思い出して、いいようのない怒りがこみあげてくるのを、おさえることができなかった。
昨夜は公民館で、村の漁協が呼びかけた「臨海工業都市造成懇談会」が開かれた。話の内容は主として漁業補償問題におかれていた。玄太たちの村も含めた一市二町三村にまたがる広大な地域を、臨海工業地域に指定し、工業都市に転換をはかる国の計画が表面化したのは、五年ほど前だった。当初、地元では反対もあったが、地元選出の国会議員や市長、町村長をはじめ、県市町村議員らを中心とする熱心な推進派のもとで、大勢は事実上決定していた。土地買収などもほぼめどがついて、残っているのは、広範囲にわたる沿岸一帯の埋め立てなどにともなう漁業補償問題にしぼられていた。
しかし、それも昨今になって、ほかの大方の漁協は妥結したといった情報がとびかい、玄太たちの村の漁民はおちつかない日々を送っていた。昨夜は、その玄太たちの村で、何度めかの話し合いがもたれたのである。
玄太が会場につくと集会はまだ始まっていなかった。そして、人々は互いに隣同士でひそひそと話し合っていた。
「補償はいくらくれえにいってくるずらか?」
「向かいの三崎じゃあ、一人二本くれえってきいたけんど……」
「漁協の幹部はどういう腹でいるずら?」
「聞くところによりゃ、しょっちゅう飲まされてるっちゅうじゃん」
「そんなこたあ、でけえ声で言わんほうがいいずらよ」
集まった人々の最大の関心は、補償金をどのくらいに言ってくるかだった。また、若者たちの間では、零細な沿岸漁業の将来を見限って、新しい工業都市への転換に期待するようなささやきも聞かれた。
そんな人々のおもわくの中で、懇談会は始められた。みんなかたずを飲んで聞くうちに、漁民の要求にちかい補償額も示された。そして、立地した工場では地元民の雇用を優先する、といった約束もつけ加えられた。また、何か新しい自営業を始めることもできるし…と、未来はバラ色の夢に包まれた話でわきたっていた。
若者は未来の街に思いをはせ、年配者らはずっと現実的で、入った補償金で家を建て替えるとか、新しい商売をあれこれ思いめぐらすなど、思い思いの期待感で会場は活気がみなぎっていた。
懇談会はこれまでに比べると考えられないほど、終始なごやかなうちに進んだ。会の主権者である工業地域造成実行組合の幹部だとか、国や県の関係者も、ごきげんだった。
そんな会場の雰囲気の中で、玄太は隅の方でひとり腕を組み、だまってみんなの言うことを聞いていた。すると、突然、中の一人が、
「そうだ、玄太じいさんがいる。この中ではいちばんの長老だし、漁も長くやってきた玄太じいさんの意見を聞いてみてえ……」
と、言い出だした。みんなはいっせいに玄太の方を振り向いた。会場はいっしゅん、静まりかえった。彼はみんなの視線にうながされるように、立ちあがった。そして、おもむろに両腕を前に突き出した。
「みんな、この手をみてごらんねえ。十五のときから五十五年間、海で生きてきたこの手を……。おれぐれえ長くやってきたものはいねえと思うけんど、この手に聞きゃあ、いちばんよくわかるずら。おれたちにゃあ、海の仕事しかできねえていうことが……」
それだけ言い終わると、かれはふたたび座り込んで目をとじ、腕を組んだ。漁民たちは、木の根っこのようなごつい玄太じいさんの腕と自分の腕を見比べた。玄太じいさんほどではなかったが、筋肉は盛り上がり、血管の浮き出たふしくれだった自分の手を、あらためて見直していた。
なんとなくきまずい空気が流れ、懇談会はそれで終わった。
しかし、大勢に影響はなかった。漁業補償は年内に終わり、来春から工事が始められることになった。
玄太は、どう考えてもいまいましい昨夜の光景を、頭の中から吹っ切ることができなかった。
「みんな浮かれているが、海がなくなったら丘にあがったカッパ同然さ」
そう思わずにはいられなかった。そして、働きもしないで入る大金などは、身につかないばかりか、けっきょくは人間を堕落させてしまうだろう。そこへいくと、海は何百年、何千年と幸を与えつづけてくれた。長い歴史がそれを証明している。それほど大きい海の恩を忘れて、埋め立ててしまうなどと簡単に言うが、新しく始める臨海工業とやらは、村人の生活にとってまだなんの実績もない、海のものとも山のものともつかないものにすぎないのではないか?
彼はむなしかった。海に働く男のロマンがあった。ちっぽけな人間があるときは戦いにいどみ、ときにはまた、慈母のふところにいるような安らぎを与えてくれた。この人間の力に遠くおよばない偉大な海!その海を無謀にも人間が埋めてしまおうというのだ。彼は怒りをこえて、形容しがたい寂しさに胸がふるえた。
やおら、彼は立ちあがった。秋の夕日ははや西に傾き、だいだい色に染まった光の帯を、波間にゆらゆらと長くただよわせていた。
玄太の足元を、満ちてきた潮があらい始めた。彼は沖に向かって歩きだした。一歩一歩踏みしめるように進んだ。海水はすねからひざをひたし、やがて腰に達した。
浜の方が騒がしくなった。誰かがしきりに玄太の名を呼んでいる。そのうちに、「船を出せ!」という声がとびかい、エンジンの音が響き始めた。しかし、玄太は後を振り返らなかった。もう胸まで水につかっていた。間もなく首から上しか見えなくなったとき、大きな波がきて、彼のからだをすっかりのみ込んでしまった。
玄太は、波間でからだがゆれるにまかせながら、なんとも言えない安らかな気持ちになっていた。それは、遠いむかしを思い起こして、母のふところにだかれているような安ど感であった。
そんな玄太の思いをかき消すように、波間から起こるエンジンの響きを耳にした。つづいて、
「おーい。玄太じいさんを見かけなかったか!を」という呼び合う声を、周辺でいくつか聞きながら、彼はしだいに意識を失っていった。
【終】

小野 連太郎
神奈川県在住の作家。著書に「無実の恋」(幻冬舎ルネッサンス・刊)がある。
「無実の恋」
私は誰の子を産み、何を愛せばいいのだろう。
一度きりの過ち。父親の違う子どもたち。ある女性の人生に落ちた光と影は変わりゆく時代に何を残すのか。