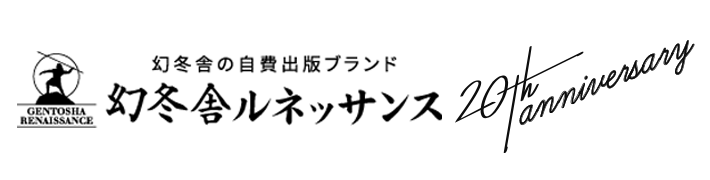本棚のある
風景
フランスの伝統的な手かがり製本「ルリユール」

“ルリユール(reliure)とは、書物を製本する技術あるいは手法である”
簡単に定義づけするならば上記の言葉が分かりやすいのですが、歴史と共にその範囲や技法は変化しました。そのため時代や場所によっては相当しない場合もありますが、それだけ長きにわたり表層を変えながらも絶えることなく存在し続けたと言えます。
日本語訳にすると“工芸製本”または“装丁芸術”と表され、動詞では“結ぶ、綴じる”といわれるように、製本方法の内容は折丁を綴じ、プレスし、革の表紙をつけたり、その他にも様々な工程を経て1冊の本へと仕上げていきます。
<ルリユールの役割>
ルリユールによって製本された書物は、社会的身分のある特権階級の貴族や聖職者、富裕層であるブルジョアたちを中心に需要がありました。
彼らのような上流階級にとって、読んで知識を得るという目的を超え、書物は貴重品・工芸作品という位置付けで大切にされていました。製本された書物を保管、蒐集することは、知的財産の保存と装飾を施し差別化することによる社会的な対面といった大きく分けて2つの目的がありました。
この記事では最も栄えた17、18世紀に焦点を絞り、時代背景も交えながらルリユールについてご紹介しようと思います。
■17、18世紀のルリユール〜本ができるまで〜
印刷業者によって紙または羊皮紙に文字が刷られ、書籍商(=書店)によって製本前のページの束、未綴じの状態である仮綴じ本として販売され、それを購入した者が製本職人のもとへ行きます。そこで自身の好みや趣向を凝らした装丁を依頼し製本されていました。
これが当時の本が出来上がるまでの大まかな流れになります。20世紀前半まではこのような工程で作られており、今では版元製本が当たり前ですが、当時はそれぞれの工程に職人や専門業者が存在していました。
<体制の変容、書物への影響>
王権統制による組合の変容
15世紀半ばにグーテンベルクの活版印刷技術の発明により印刷業が飛躍的に進化、効率的に大量の印刷が可能になりました。フランスにもその技術が輸入され、同じように本の生産は盛んになります。
しかしこの事がきっかけとなり、これまで協力していた職人同士の組合や業者間の連携体制が崩れ、作業や利益などについて摩擦が生まれ、職域で揉めるようになってしまいます。
その対策として1686年王令により、これまで兼業が許されていた組合が分割され、本が出来るまでの工程が厳しく明確に分かれました。
例えば、書籍商は製本業との兼業が認められず仮綴と紙表紙まで、一方で製本職人(箔押し職人も含む)は素材や綴じ方などは限定されながらもルリユールの特権を持つようになります。加えて各々、他の業者の専門道具を持つ事が禁止されました。(例えば製本で使用する大型のプレス機は製本職人のみしか持つ事が出来ないなど。)
これにより各技術が散漫にならず、フランス装の技術が他国に比べ卓越した分野を築き、様々な技法や表現の成長に繋がったと思われます。
各分野の競合と発展
このように王権統制によって印刷業者・書籍商・製本職人が分かれ、製本職人にのみルリユールの特権が与えられる形となりました。
とはいっても、全てがその限りではありませんでした。例えば書籍商は仮綴じ本を売る際に、製本行為(羊皮紙の使用やカルトン((製本用の厚紙))や革を使った表紙作りなど)は認められていませんでしたが、薄いカルトンと模様紙で表紙を作り販売するようになっていきます。ルリユールの表紙作りの構造を模倣したやり方です。
少しずつ仮綴じ本は、ルリユールの製本構造に寄っていく形となり、ルリユールによる高価な製本ではなく、安く大量に作れる模倣品や代替物が出回ります。この模倣行為は、仮綴じ本の質の向上になりました。様々な技法も生まれ、単純に庶民のための安い未完成な本としてではなく、製本しないまま紙のデザインによる本が広い層に求められるようになります。その中には上流階級も含まれていました。
それに対抗するために製本職人は新たな綴じ方や装飾を考え、ルリユールの向上へと繋がっていったようです。
庶民のための仮綴じ本と上流階級のためのルリユール。大量生産と伝統工芸。安価と高価などというような単純な二項対立ではなく、成熟した生産基盤と紙による模倣品の進出を受けて、製本職人が創意工夫し技術の向上と独自性の開拓といった構造になり、その循環でさらにルリユールの世界に厚みが生まれたのです。
このような時代背景や社会現象によって、ルリユールは構造や外観に影響を受けていきます。
これら全てがルリユールの広く深い世界を作っていったと思われます。
<人と書物の関わり>
こうして様々な層の人に向けて、様々な形をとりながら本は生産されるようになり、18世紀末になると書籍文化はさらに浸透し、多くの人の生活に根付いていきます。
王族や貴族ともなるとお抱えの製本師を持つことも珍しくありません。雇い主の書物への想いと贅を詰め込み作られた書物は、素晴らしい工芸的作品として受け継がれていきます。代表的なものにグロリエ叢書があげられます。
一方で作品というよりは、使う本(読む本)としての楽しみ方も広がっていきます。
胸ポケットに仕舞えるサイズになったり、仕舞った先で開かないようにケースを作ったりなど、本の周辺の小道具も賑わいを見せるようになります。また読書を中断しても再開できる工夫として、栞紐が付くようになったのもこの頃といわれています。
読書を楽しむ人、装飾美を愛でる人、蒐集する人。
本は時代と共に複合的な役割を果たし書籍文化を築いていきます。ルリユールは装飾的、工芸的な要素を多く含みながらも、組合同様他の要素を持つ分野同士、呼応し合う関係となり発展していきました。
■ルリユールの様々な技法
フランス装に限らず、ヨーロッパにおける洋式製本は16世紀には広く伝わっていました。
17、18世紀はそのベースから様々な技法が派生し、デザインの幅が広がり、装丁のクオリティーが成熟していきます。この頃になると、ルリユールのイメージとして代表的なモロッコ革による装丁が定着しました。その他に当時のルリユールでよく見られた技法や装飾の一部をご紹介します。

表紙デザイン
フェールといわれる木製の柄に刻印をさしたものを使用します。コテの一種です。始めは背表紙などにタイトルを刻む際に使われた活字フェールが発展し、様々な模様を本の表紙に刻む事が出来るようになりました。刻印の組み方やコテの動き、模様によって多彩な表現を可能にし、表現技法として定着しました。(ポワンティエ装丁・ダンテル装丁など。)

小口装飾
裁断して切り揃えられた小口(天のみ、もしくは小口すべて)にも装飾を施していました。最も好まれたのがドリュールといわれる、金箔を用いた技法です。日本では小口金箔といわれます。見た目の絢爛さだけではなく、ホコリからの保護の役割も果たしています。時代や国によっては、混合率など質の良し悪しの違いがあったといわれています。

他にもマーブル、赤色染め、黒色染め、吹き散らし、さらには小口金箔の上に点描で絵柄を書くこともあり、小口の装飾一つだけでこれほど多くのバリエーションがありました。

模様紙
18世紀には色とりどり、様々な模様紙が流行しました。マーブル紙、糊染や木版による模様紙などがその代表です。その多くは見返し部分に使用され、中には書物の内容と関連性のあるデザインが使われるなど、製本による美術的な表現の一つとして重要になりました。
■最後に
このように世情にも大きく影響を受けながら、フランスのルリユールは特異の発展を遂げました。1冊1冊が職人の手作業によって作られ、作業工程ひとつ取っても技術やこだわりが凝縮されています。知的財産としての価値だけでなく、美術・工芸の視点からもその価値を確立したルリユール。長い年月の中で発生した様々な因子と職人たちの創意工夫、愛書家や蒐集家の熱意が、今現在私たちが手にする紙の本を形作っていったのだと思います。
参考文献
- 『書物と製本術』みすず書房
- 『装丁ノート製本工房から』集英社文庫
- 『西洋製本図鑑』雄松堂出版
- 『書物の歴史』白水社
幻冬舎ルネッサンス新社では、本を作る楽しみを自費出版という形でお手伝いしております。
原稿応募、出版の相談、お問い合わせ、資料請求まで、お気軽にご連絡ください。
-
ポイント1
お問い合わせいただきましたら、担当の編集者がご対応いたします。
-
ポイント2
原稿内容やご要望に沿ったご提案やお見積もりをご提示いたします。
-
ポイント3
幻冬舎グループ特約店(150法人3,500書店)を中心とした全国書店への流通展開を行います。