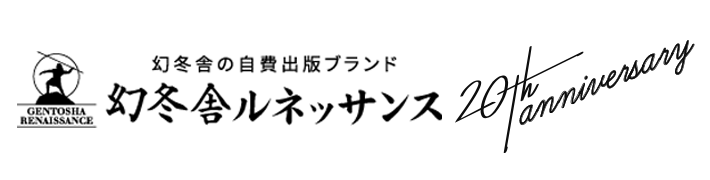私にとって出版は自分がチェンジする、
第二の人生がスタートするきっかけでした。
『ヴァネッサの伝言』
剣は使うが血は流さぬ。強い意志と決意を胸に、大きな賭けに出るシルヴィア・ガブリエル。仮死で生まれた運命の子は、はたして未来への扉を開くことができるのか!?生きることの意味と遺される者の想いを深く描く、感動のヒューマン・ファンタジー。

幻冬舎ルネッサンスで『ヴァネッサの伝言』を皮切りに『アイミタガイ』まで、計4冊の小説を出されている中條ていさん。現在、『アイミタガイ』は幻冬舎文庫に収録され、映画化の話も出ている。今、最も注目されている作家のお一人に、『ヴァネッサの伝言』を書くに至った経緯から、編集者とのやり取りなどについて伺った。
―なぜ小説をお書きになろうと思われたのでしょうか。

中條 それは本当に突然だったのですが、兄が亡くなりましてね。80歳になった両親を残して先に死んだわけですから、これは困ったことになったなと思ったんですよ。残された両親たちをどうやって慰めたらいいんだろうって。どんな慰めの言葉でも、やっぱり親に対して子供が言っても通じない部分がありますからね。それを何か違う形、例えば、小説にしてそこに思いを込めたら、親にも伝わるんじゃないか。また、書いておけば、命というのは限られたものですからいつか私も死にますけれど、その時点で私が感じたことがずっと残って、子供や孫にも伝えていけるのではないかなと考え、それで本を書きたいと思ったんです。
―それを『ヴァネッサの伝言』という小説の形にまとめたわけですけれども、手紙やエッセイではなく、そもそも小説にしたのには理由がありますか?
中條 ええ、エッセイだとしたら、あくまで私の言葉で発信しますので、両親はたぶん、どうせ娘の言葉だと思って聞かないですよね。それよりも、自分たちとは全然関係のない間接的な形にした物語の中でなら、両親は素直に私のメッセージを受け取ってくれるのではないかと思ったんです。
―周りのご家族の悲しみも癒すためでもあったということですか?
中條 いえ、悲しみを癒すっていう気持ちは私の中にはないです。癒さなくていい。むしろ思い切り悲しんで、人は生まれたからには死ぬ、その決まり事の中で、じゃあ、生きるってどういうことなのかを考えてみてほしかったんです。かわいそうと嘆くのじゃなく、死んでいった人がどう生きたかを見つめてあげることが大切かなと思っているので、それを伝えたかったですね。
―それまで本を書こうと思ったことはなかったのですか?
中條 はい、一切思わなかったです。私は子供のときから本が書きたいとか、小説家になろうとか、そんなことは全く考えたこともなく、それが突然思い立ったんです。何月何日って言えるくらいはっきりと。
―そのとき、伝えるには本しかないのだと。
中條 いえ、書こうと思ったとたん、私の本が本屋さんで平積みになって置かれているところのイメージがハッキリと見えてしまったんです。そうなったら嬉しいなと思って、ただそれだけ。何の疑問もなく、本を書いたらそうなるんだと思い込んでいました。何にも知らなかったんですね。ですから、思い立ってまず書きは始めて、書き上げた後になって出版ってどうやってするんだろう、ってはじめて考えたんです。
―大体どのくらいで書き上げたのですか?

中條 8カ月です。最初から8カ月で書き上げようと決めて、7月21日から書き始めたので、仕上がりは3月21日にしようと。ただ、もう書き方は全然わからなかったんですよ。どうやって書くのか、最初の3日間くらいは書いたものを読み直す度に、自分で笑ってましたね。あまりにもお粗末で。でも、3日目を過ぎたころから、まずプロローグが書けて、あらっと。少しコツがわかったみたいで、それからは順調でした。
―文章ができて、それでどこの出版社に持っていこうかと。
中條 そうです。思い立って書き上げたのはいいけれど、はて出版ってどうやってするんだろう、って。それで慌ててネットで調べたんですけど、どこの出版社にも素人が書いた作品を受け付けてくれる窓口が開いていなかったんです。
本を出すためには賞をとらなければいけない、とも書かれていて、へぇー、そうなんだとびっくりでしたね。だけど賞って、どうやって応募するのかもわからないし、枚数にも制限があるらしいと、それもはじめて知り、愕然としましたよ。600枚以上書いてましたから、尺が長すぎて、もう無理と。しかも、コンテストの下読みの人たちは最初のところしか読まないので、そこで読者の心をつかめないような作品ではだめだとも書かれていて、あーあ、と思いましたね。
―賞には応募されなかったのですか?
中條 私の作品は主役が死んでしまうような話でしたし、これはちょっと難しいなと思いました。そこで、今度は自費出版についてネットで調べてみたんです。自費出版の本でも、本屋さんに並べられていますが、どこの社の本でも全部一緒に並べられていて、「余分な本」みたいな感じで置かれています。頑張ったのにそれじゃ、ちょっと悲しい。だって最初のイメージは平積みでしたからね。たとえ自分でお金を出していても、商業出版のように扱われる本じゃないと、と思いました。その商業出版と遜色のないような本を出してくれるところはないのかなと探していたら、幻冬舎ルネッサンスに出会ったわけです。
―ジャンルと全然関係のない棚にポンと置いてあるだけでは目に留まりませんからね。
中條 そうですね。素人が自費出版して、親戚に「出したから読んでください、買ってください」とお願いするのだったら意味がないといいますか、出す以上は、一生懸命書いて、プロが書いた作品と同じように並べていただける、そのためには自分も精度を上げていかなければいけないし、それが結局自分のためにもなるだろうと思って、この道を選びました。
―出版されて、反響もあったと思いますが、具体的には身の回りでどうでしたか?
中條 もうものすごかったです。新たにいろいろな素晴らしい方ともお友達になれました。人間関係が大きく変わった感じでした。
―歴史物に限らず、読書体験は多いのですか?

中條 人並みくらいですけど。読書家の方と比べたら、私はそんなに読んでいないほうかもしれません。読んでいた時期はありますけれど、子育てで忙しかった間は、もう本当に10年間に1冊読んだかなってくらい。
―執筆を進めていく上で苦しかったことはありますか?
中條 物語の展開には、あまり苦労しないんです。プロットなども、一瞬で生まれてくる。でも、あとの作業、書くことって、それこそ手縫いで刺繍していくような作業ですから、入口から出口まで全部わかっているだけに、まどろっこしいんですね。映像は簡単に目に浮かんでくるのに、ここのものをあそこに持っていくだけのことでも逐一書かないと伝わらない、そういうのは気が焦るんですよ。もう早く先へいきたいのに、なんかよちよち書かなければいけないみたいな。
あと、既に出来上がっているものが頭の中にあるので、やっと書いたものを読んでみて「こうじゃない」というのも、よくわかりますね。だから、またやり直し。
―編集者とのやり取りで印象深いエピソードはありますか?
中條 そうですね、大変だったというのはなかったですね。楽しい作業だったなと思います。他人が私の作品の中に入って、同じような目線で考えてくださるっていうのは、すごく嬉しい作業でしたね。なんかこう、プロになったような。家族や子供でも、私の脳内のものは共有することはできませんでしょ。編集者さんとは、唯一それができた人のような感じがしましたね。それまで執筆は孤独な作業でしたが、編集者の方にお会いして、この人はどう思うだろうか、という対象がいることで考えやすくなりました。「私、実はここ気に入らないんだけどな」って思っている箇所があるとすると、言わなくても向こうが先にチェックしてくる。そういうとき、さすが、ってうれしくなりましたね。
―この人はいい編集者だな、というポイントはありますか?
中條 それは自分の脳内に招き入れるわけですから、こちらの感覚でものを感じたり考えたりしてくださるというか、そういう共感がある方がいいですよね。原稿の中には、自分ではオープンにしていない気持ちが隠れているわけですけど、そういう奥にあるものを編集者に悟られてると感じるときがあって、それは一方ではとっても危ういことですけれど。でも、そうなったときにものすごく信頼感が生まれますし、どう思うかというのが尋ねやすくなりますね。
―執筆中に次の作品の構想が浮かぶことはありますか?
中條 書いているときは、いつも8カ月区切りでやっているので、他が浮かんでも、そっちを見ないようにしています。で、一つが仕上がっちゃうと、そろそろかなって感じで見えてくる。でも、面白いことに構想って、お風呂に入って出てきた瞬間にボーンと浮かんできたり、そんな感じなんですよね。
―最後にこれから執筆する方々に、メッセージをお願いします。
中條 自分に起きたことを振り返ってみますと、人間って何歳になっても自分が考えてもいなかったようなことが、ある日突然起こるんだなと思いますよ。だって昨日と今日とが全然違うっていう状態が、まさにそれが自分に起こったわけですから。だから、よく人に「何で書くようになったの?」とか、「書いたときにどんな感じ?」だとか、聞かれるんですけど、「あなたが明日からスケート始めたとして、意外に滑れてオリンピックの強化選手になっちゃったよ、みたいな感じは起きると思うよ」って答えています。それまで全く思いもよらなかった人生がたった一歩から始まる可能性っていうのも、あるんだと思います。私にとって出版は、自分がチェンジする、第二の人生がスタートするきっかけになったと思います。
あなたも出版してみませんか?
お気軽にご相談ください。
03-5411-7188
営業時間:平日10:00〜18:30